- 一般財団法人カケンテストセンター
- 試験を探す
- 機能性評価
- 快適機能(暖かさ/爽やかさ)
- 光吸収発熱性試験(JIS L 1926)
光吸収発熱性試験(JIS L 1926)
概要
光によって発熱する生地に対し、光を照射した時の温度変化を測定する試験です。炭化ジルコニウムや酸化チタン化合物など、繊維に練り込まれた物質が光を効率よく吸収し、光の放射熱を熱エネルギーに変換することで暖かくなります。この機能は「光吸収発熱性」と呼びます。
目的
日光を吸収して発熱する生地の評価が目的です。これら生地は、特に屋外で着用する冬物衣料などに使用されます。
試験対象品
- ゴルフウェア
- フィッシングウェア
- トレッキングウェア
- ジャケット類
- パンツ類
- コート類
試験方法
JIS L 1926
概要
光源に、人工太陽光を使用することが特徴です。
試験方法
- 試料裏面に受熱体を接触させて配置し,試料が光を吸収して発した熱を受熱体に吸収(伝導)させます。
- 光を照射して30 分後の試料を装着した受熱体と、裸の受熱体(ブランク)、ぞれぞれの上昇温度を測定します。
- 次の式で光吸収発熱温度差を求めます。
ΔT=⊿Ts-⊿Tb
ΔT:光吸収発熱温度差(℃)
ΔTs:試料の平均上昇温度 (℃)
ΔTb:ブランクの平均上昇温度 (℃)
 |
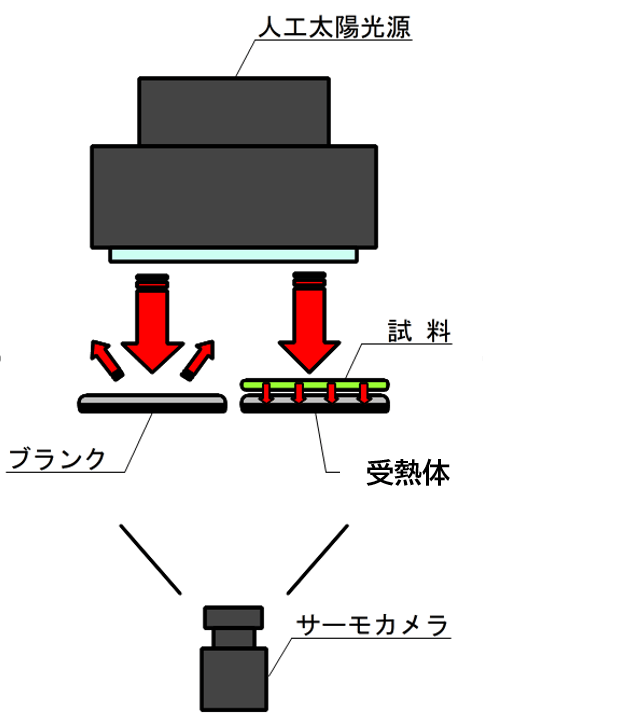 |
|
| 光吸収発熱性試験装置 | 装置モデル図 |
試験結果例
| 試験項目 | 試験結果 | |
|---|---|---|
|
光吸収発熱温度差 (ΔT) |
対照品 | 13.7℃ |
| 光吸収発熱素材 | 17.1℃ | |
| 試験方法: | JIS L 1926 |

